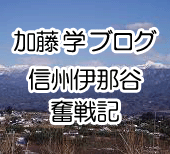加藤学の政策
加藤学の政策
こちらでは、過去に発表した加藤学の政策などを掲載しております。
加藤 学 の緊急重点政策 【国民の生活が第一】
2012年8月
正義なき消費増税は廃止します。
-
増税よりもデフレ脱却
デフレ状況下で増税をすれば、経済はさらに冷え込み、見込んだ税収さえもあがりません。1997年に緊縮財政と同時に消費税を5%に引き上げた時は、結局税収は増えませんでした。まずは経済を安定した成長軌道に乗せることに全力投入すべきです。 -
社会保障の明確なビジョンを
3年前に国民と約束した後期高齢者医療制度廃止、最低保障年金、年金一元化、歳入庁設置など、掲げた政策の方向性を堅持したまま、社会保障全体のビジョンを明確化し、財源の議論に入るべきです。国民負担の議論が先行するのは本末転倒です。 -
身を切る行財政改革を
天下りの禁止、政府関連法人の整理をまず徹底します。その上で、予算の総組み替えを可能にするための国家公務員の人事制度改革、国家戦略局設置、国会議員定数削減など、本質的な改革を断行し、税金の使い方を改めます。
増税「待ったなし」というのは、国民に対する脅しにすぎません。
国の債務がGDPの2倍の1000兆円になったと財政危機を強調する声があがりますが、一方日本政府は、約500兆円の金融資産を持ち、国全体で、世界最大の対外債権(250兆円)を保有しています。「今増税に踏み切らないと日本国債が暴落する」というのは脅しにすぎません。このまま債務を放ったらかしにはできませんが、国債の90%以上が国内保有の日本国債は、債券市場でも安定資産として世界から資金が集まっている状態で、長期金利も低く推移しているのです。「待ったなし」というほど危機的な状況ではありません。
TPPより、日・中・韓・ASEANの経済連携を。
TPPは、関税ゼロを農産品にも例外なく適用する経済連携協定で、保険、医薬品の規制、食の安全、公共事業の基準もアメリカの要求に合わせていくものです。そもそもアジア市場を狙うアメリカの政治的戦略であり、日本の農業や医療制度に多大な影響を及ぼすばかりか、日本全体の利益にもなりません。成長著しいアジアとの経済連携を強めていくことは重要です。しかし、その道筋はTPPではありません。それよりも、気候・文化・食生活など共通点も多く、隣国としてのつながりの深いアジアの国々とのFTAなどの経済連携強化をベースに進めていく方が、近道であり、アジア全体の繁栄に繋がります。日本の国益にならないTPPへの参加表明には一貫して反対して参ります。
原発ゼロ社会の推進で、新投資・新産業を創出。
日本産業の突破口はエネルギーシフト
-
エネルギーの地産地消
地域の森林、水、太陽、風力、地熱を利用した小規模の発電所、熱施設を整備し、地域内でエネルギーを自給自足できる社会をめざします。国は初期コストの支援と、発送電の分離自由化を進め、地域の雇用を産む新産業の育成を支援します。 -
新エネ対応の新投資を支援
再生可能エネルギーの普及のためには、ネットワーク型で電力の安定供給を可能にするスマートグリッド、蓄電池技術が必須。技術協力と共に新エネ対応の住宅、乗り物、家電など、関連分野での新投資を加速させるため資金面・制度面で支援します。 -
エネルギーの国際ネットワーク
脱原発を着実に進めるためには、安定した代替資源の確保が不可欠です。日本近海の新しいガス田の開発、ロシアとのガスパイプライン、東アジア地域の国際協力ネットワークで電力を融通し合う海底ケーブル敷設など、新プロジェクトを推進します。
党の看板ではなく、国民との約束を守りたい。
2012年7月
7月4日、7年間お世話になった民主党を離れる決心をし、離党届を提出してまいりました。その理由は、国民との約束を軸とした政治という民主主義の基本を、野田政権とそれを支える執行部が忘れてしまったことに、一人の政治家として、一人の人間として許せなかったということにつきます。
私は3年前、「政治を変えてほしい」という国民の大きな期待を受けて、国会に送り出していただきました。その時に多くの国民が期待したことは、既得権益者のしがらみにがんじがらめになった政治を国民の手に取り戻すこと。つまり、組織のしがらみを超えて国民一人ひとりの選択によって新しい政権を作るということでした。
しかし、政権をとってから3年になろうとしている今、民主党は、「政治を変えてほしい」と願う国民の期待と、私のように政治を変えたいと飛び込んできた若い志を受け止められる包容力を残念ながら失ってしまいました。
私は3年前の選挙で、政治主導で予算の総組み換えをする、年金を含む社会保障の抜本改革をする、地方と中央の関係を変えて、地域で自由に使える財源と裁量権とを用意する、と訴えて勝たせていただきました。同時に消費税はこれらの改革の前にはやらない、野田総理の言葉を借りれば、「シロアリ退治なき増税はない」と言ってきました。なのに、こうした国民との約束は、民主党内で政策変更のコンセンサスもとれないまま、いとも簡単に破られてしまったのです。
状況によって政策は変わっても仕方ないのだ、と言う人がいます。それは一理あります。しかし、マニフェストは国民との契約ですから、契約の変更には、双方の合意が必要です。仮に消費増税をやらなくてはならないならば、自民党や公明党とこそこそと合意文を作ることよりも、国民や民主党の支持者、そして私たち党所属の議員が納得できるよう、タウンミーティングや党内の話し合いにもっと時間をかけてある程度のコンセンサスを得ることが重要です。世論調査等でも現時点での消費増税に多くに国民が反対し、地域を代表している議員の多くが反対している状態で、一方的な政調会長一任宣言で幕引きされるということは、民主主義の道理上あってはならないことです。
私は、消費税増税法案に反対票を投じた後も、民主党内に残って党内から法案の修正や党内改革ができるのではないかと思い、一度は党に留まる決心をしました。しかし、実際に党員資格停止の処分を受けると、党内での発言権も議決権もなくなり、地元での活動も制約されることがわかりました。つまり、党内から消費税増税撤回をしていく道はもう絶望的であると判断し、処分が正式に出たことを受け離党を決意しました。
離党への決心がつくと、もう心が揺れるのはいやだと思い、事前に支援者や関係団体、そして同僚議員にも告げることなく、即、幹事長室に離党届を提出に行きました。「前に一言欲しかった」というお叱りを覚悟の上での行動です。そのことは、ご心配していただいている方にたいへん申し訳なかったと率直にお詫びしなくてはなりません。しかしながら、「党内で頑張ってくれ」という声の一方で、「なんで離党しないんだ、筋が通らないぞ」というお叱りの声も多く寄せら
れていたのも事実であり、思い悩んだ末、一人で決断させていただきました。
今後は、消費税増税を阻止するために、同じ思いを持つ同志と共に、野党の立場で国会活動の中で行動してまいりたいと思っています。私自身が3年前の選挙で国民の前で約束したことを守っていくための行動です。党の看板を守るよりも、約束した政策のために命をかけて頑張ることこそが私の目指した政治家の姿であると思っています。悔いはありません。今後は、新しい党「国民の生活が第一」の一員として活動してまいります。一人の人間、あるいは政治家として信念に基づいてとった私の決断を、多くのみなさんが必ず理解してくれるものと私は信じております。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
加藤 学 の重点政策【地域自給力倍増宣言】
2009年
人に投資し、人材を自給する
- 子供手当て、月額26,000円を中学卒業まで支給。
- 高校授業料を無償化。大学進学者への奨学金を拡充。
- 伊那谷に大学・研究機関を設立し、世界に向けて人材を供給。
生命を守り、安心を保障する
- 医師数を1.5倍に増やし、医師派遣制度で地域で安定的に医師を確保。
- 産科医療を地域の実情に応じて見なし、出産の経済的負担を軽減。
- 年金を一元化し、最低保障年金月額7万円を保障。
- 全労働者に雇用保険を適用。介護労働者の賃金を月額4万円アップ。
- 郵政3事業(郵便・金融・保険)一体的サービスを保障し、地域での利便性を確保。
食糧・エネルギーの地産地消
- 戸別所得補償制度で農業経営を安定させ、国内食糧自給率を60%に。
- 森林整備・林道整備・木材流通の簡素化で、木材関連産業を地場産業として再生。
- 太陽光発電、バイオマスエネルギー発電の推進でエネルギーを自給。
長野県の地図を南北ひっくり返す
- 中央高速自動車道の無料化、三遠南信自動車道の早期実現。
- リニア新幹線の伊那谷停車駅設置と飯田線の複線・高速化。
官僚・世襲支配から脱却し、税金を賢く使う。
- 天下り廃止。世襲立候補の制限。国会議員が官僚を人事・政策面でコントロール。
- ヒモつき補助金の廃止。地方への一括交付金支給で地方分権の推進。
- 所得税累進強化、金融取引税強化、環境税の導入で、財政を健全化。
寛容でオープンな国へ
- 平和省を設立、憲法9条を基本に平和外交をリード。
- 外国人労働者・移民を受け入れ日本を多民族共生型社会へとシフト。
- 選択的夫婦別姓制度の導入で、「家」に縛られない「個人」を確立へ。
ゼロから作り出そう。〜踏襲から創造の政治へ〜
世界の情勢は大きく変わり、わが国も日本かつての日本ではない。人口が減り、医師もいない、大きな経済成長も望めなくなった。根本から日本の体質を変えなくてはならない。
官僚は前年の予算に引きずられる。世襲議員は引き継いだしがらみに縛られる。前例踏襲型の政治では激動の時代の変化に対応できるはずがない。
ゼロから創り出そう。予算も制度も理念も。明治以来の手垢のついた官僚主義から脱却し、国民主導の新しい政治を私たちの手で実現しようではないか。
敵は、私たちひとりひとりの心に潜むあきらめと臆病、勇気をもって一歩を踏み出し、がんじがらめのしがらみに打ち勝つことから、私たちの未来が切り開ける。
不景気に勝とう。
しがらみに勝とう。
加藤で勝とう。
(第45回衆議院議員総選挙)
リベラル宣言。寛容と共生の国へ。
2007年9月1日
小泉政権の市場原理主義的な経済政策によって、地方経済は疲弊し生活格差は拡大しました。その後を引き継いだ安倍首相は、「再チャレンジ」を口にしながらも、国民を苦しめる市場淘汰路線に修正を加えることなく、大企業に有利な自由競争を煽るだけの「成長路線」をむなしく言い放っただけでした。その一方で、「戦後レジームからの脱却」を掲げ、復古主義的な理念を強制することで、国民の不満を力で封じ込めてきました。教育や報道への国家強制力の強化、憲法の改正、米軍追随の安全保障政策の推進、戦前の歴史を正当化しようとする歴史観。首相が唱える「美しい国」の本質とは、国家権力側にとっての「美しさ」にすぎなかったのです。
先の参院選による自民党の惨敗は、そうした安倍政治の理念そのものに国民が「NO」を突きつけた結果でした。国民が今政治に求めている政治とは、憲法の改正を急ぐことでも、国家主義的な教育を強制することでもなく、生まれた地域で安心して生活し、子どもを育み、老後を健やかに全うできる国の仕組みをどう作り上げるかであるということが、「国民の生活が第一」を掲げる民主党の勝利によって明らかに示されました。
ここ伊那谷(長野5区)では、1996年に新進党の中島衛氏が衆議院で議席を失い、1999年に社会党参議院議員・村沢牧氏が死去して以来、自民党が衆参国会議員の議席を独占してきました。衆議院議員の宮下一郎氏は、安倍首相が提唱する米国追随反中国を基調とする「価値観外交」議連のメンバーとして、国家主義的・復古主義的な安倍政権の路線を支える役割を担っています。そして参議院議員の吉田博美氏は、宮下氏との二人三脚をアピールし先の参議院選で再選を果たしました。安倍政権のもと、日本が戦後民主主義から大きく逸脱しようとしているときにあっても、伊那谷では一党支配による既得権益としがらみに縛られ、こうした流れに抗うことさえままなりません。
自民党政権が進める市場原理主義や復古的国家主義がこの伊那谷の生活を豊かにするものではないことは明らかです。政治をしがらみに縛られた一部の既得権益者の手から、「普通の生活者」の手に取り戻すため、この伊那谷に新しい国会議員を誕生させ、新しい政治の風を起こし、この地を風通しのよい地域に変えていかなくてはなりません。
そこで、伊那谷の非自民勢力の結集を広く呼びかけます。その基本理念は、リベラル(liberal)です。リベラルとは、「自由」「寛容」「共生」の意味で、国家権力による抑圧からの「自由」、格差の固定や世襲社会からの「自由」、そして固定概念やしがらみにとらわれず、新しい考えや価値観に寛容な社会を実現するための理念です。具体的には、戦後日本の平和主義、民主主義の根本である日本国憲法を尊重し、異文化、異民族、マイノリティー、社会的弱者に対し包容力を持って、さまざまな価値観を持った人が共に生きることのできる社会をめざしていきます。
長く続いた自民党政権は、「鈍感力」などという言葉が堂々といえるほど、その政治感覚は国民の現実の生活感からかけ離れてしまいました。また、参議院選敗退の責任をとって政策の軌道修正をはかるという潔ささえも自民党は失っていまいました。今や、自民党政治に代わる新しい政権を打ち立てることによってしか、国民の声に真摯に耳を傾ける政治を実現する道は残されていません。その一歩は、この自民王国の伊那谷においても、自民党に代わる新しい政治勢力を作り上げることです。
いざ、集わん、リベラルの旗の下に。その旗は、統一のイデオロギーや短期的な利益を追求するものではありません。「自由」・「寛容」をキーワードに党派を超えて、非自民、脱しがらみの勢力が結集し、日本国の戦後民主主義と平和主義の理想を守り、発展させる戦いを始める旗印です。さあ、逆行する歴史の単なる傍観者であることをやめ、自分の足で、一歩前へ、踏み出そうではありませんか。
伊那谷から政治再生。「淘汰の政治」から「共生の政治」へ。
次期衆議院選挙民主党公認候補第1次内定を受けて
2005年11月23日
2005年11月22日に民主党本部常任幹事会の決定をもって、次期衆議院議員選挙の長野5区の民主党候補者の公認をいただきました。前回の選挙で大敗を喫した民主党は、党の再生をかけて小選挙区で戦える選挙区と候補者を厳しく選別、その結果、第1陣の戦士として、私を含め全国で54人が公認内定を受けました。
加藤がくは、小泉政権発足以来拡大する都会—地方間の収入格差や教育機会格差を食い止め、伊那谷で暮らす人たちが、伊那谷に誇りをもって子供たちを育んでいける社会を取り戻すために、田舎育ちの庶民の気持ちが理解できる者の一人として、その声を国政に届けていきたいという一心で立ち上がりました。
今の政治はお金の論理だけが先行する政治になってしまいました。「官から民へ」という聞こえのいいスローガンも、「民」が示す意味は、「民衆」の「民」ではなく、「民間企業」の「民」に過ぎないということがはっきりわかってきました。「民間にできることは民間に」を合言葉によって、資本力のある強い大企業やマネーゲームに興じてテレビ局や球団の買収を試みる起業家を「勝ち組」として持ち上げる一方で、「自己責任」の名の下に、低所得層や高齢者、さらには障害者への負担を強化し、民衆の生活に負担を負わせています。
「小さな政府」という概念は本来、公共サービスの質を落さずにいかに効率化するかということです。単に財政規模を小さくし民営化すればすべてが効率的になることはありません。サービスの種類によっては国に任せたほうが効率的な場合もあります。公共サービスの中身をしっかり吟味し、サービスの担い手を国、地方、または民間企業にどのように振り分ければ、最も効率的な政府運営ができるかを議論するのが重要なのですが、現政権は、題目のように「民営化」を唱えるだけの「民営化教」に妄信し、政府の役割をそぎ落とすことで、政府の責任をなるべく逃れようとしているのです。
「民営化教」の論理は「淘汰」の論理です。競争によって強いものが生き残り、弱いものは死んでいく。そうした論理は企業の経済活動においては有効であっても、社会一般にあてはめることには無理があります。社会は多様です。体の強い人もいれば弱い人もいます。住んでいる場所も受けた教育も生活環境も、そして親から受け継いだ資産も人によって異なります。こうした競争の初期条件を無視して、「さあ競争だ、生き残れないのは自己責任だ」と言い切れるでしょうか。経済の論理を無理矢理に社会一般に当てはめると、社会は実に殺伐とした暖か味のないものとなってしまいます。
だからこそ政治が必要なのです。しかし、ここで必要な政治の機能は、そうした競争を制限することでも、競争で生き残れない人を甘やかし救い上げることではありません。自由主義経済下での政治の役割は、誰もが同じ条件で競争に参加できるための環境を整えていくことにあります。ゴルフには誰もが楽しむことができるようにハンディキャップルールがあります。実力に応じて段々にハンディキャップをゼロに近づけていく。そのように政治の機能とは、初期段階ではレベルの格差があっても、できるだけ多くの人が競争に参加できるように条件を整え、その条件を透明で公正なルールで管理していくことにあるのです。生まれた環境や場所にその後の人生が規定されてしまわないために、全ての人がまず同じスタートラインに立てるようにすること。そして失敗しても何度も挑戦できる環境を整えることが必要です。政治の役割は、「淘汰」によって切り捨てるのではなく、より多くの人にチャンスを与え、多様な人々が競争社会にあっても「共生」できる環境を作ることなのです。
現在進行する他者への思いやりの心を失った「淘汰の政治」によって、子供たちの手足には4つの大きな鉛の玉がくくりつけられてしまいました。
1つ目は、親たちの世代が背負ってしまった国の借金1000兆円をひたすら返し、多くのお年寄りの年金を支えていかなくてはならないという負担。
2つ目は、親たちがなりふり構わずに開発し汚してしまった地球環境の下、気候変動と新種の伝染病に怯えて暮らしていくという不安。
3つ目は、国の教育政策の失政によって、公立学校の教育のカリキュラムにだけ頼っていただけでは、国際社会を勝ち抜いていけるだけの知識と教養を身につけることが困難になってしまっているというハンディ。
そして4つ目は、親たちの怠慢によって戦後60年をたっても隣国との間できちんと戦後処理ができてないために、隣国と外交関係を未来志向的に発展させようとしても、なかなか乗り越えられない歴史問題という外交上の足かせ。
これら4つの重荷によって、子供たちの未来への希望や大きなことに挑戦しようとする気持ちは削がれ、無気力でナイーブな子供たちが増える結果となってしまいました。
それゆえ、私が目指す「共生の政治」とは、子供たちに課せられた負担を取り除き、絶望の淵から救い出す政治でなければなりません。それは、自然や他国の歴史・文化を敬う寛容の精神を培うとともに、あらゆる世襲や縁故主義を排し、教育機会、就労機会、事業参入機会を保障し、社会の健全な競争の土台に人々を確実に載せていく政治なのです。
弱者・地方切り捨ての「淘汰の政治」によっては、伊那谷の未来に明るい展望は描けません。都市と地方、日本と隣国、お年寄りと子供たちがお互いにバランスの取れた負担と緊張関係をもって共存していける社会とはまさに、「誰もが挑戦できて、まじめさが報われる社会」です。伊那谷の子供たちが郷土を愛し、未来に大きな希望を抱くことができるために、加藤がくは、今ここに、新しい政治の狼煙を立ち上げ、次なる戦いに挑むことを宣言致します。
私の政治への思い
民主党候補者公募 応募小論文
2004年
戦後60年、過去の歴史を見つめ直し新たな国づくりを進めるべき時にあって、政治の停滞は目に余るものがある。小泉首相は、財政再建、地域経済の活性化、年金改革、教育改革、そしてアジア諸国との歴史問題の解決と友好関係の構築といった政治の重要課題を置き去りにして、国民の半数が反対する自衛隊のイラク派遣や靖国神社参拝に異常な執着を見せる独りよがりの政治を続けている。「民間にできることは民間に」を合い言葉に進めた理念なき「小泉流構造改革」は、ITとマネーゲームの一部の成功者を「勝ち組」と祀り上げる一方で、地方の町や村で真面目に生活をしてきた人たちの悲痛な叫び声を「痛み」の一言で払いのけ、「人生いろいろ」とせせら笑う。
進行する「勝ち組」と「負け組」の線引きは、単なる一世代の所得格差や都市−地方の格差に留まらない。「ゆとり教育」という失政によって、公立学校が疲弊し、塾や私立学校への教育依存が高まったため、子供の教育機会が親の収入や住んでいる地域に大きく左右されることとなってしまった。田舎の公立学校と東京の私立学校との教育水準の格差は、子供たちの将来の職業の選択や収入に大きな影響を与え、教育機会の格差が社会階層を固定化する構造が現出した。そして、その階層の固定化が、将来の膨大な国債償還と年金負担の不安とあいまって、若い世代に大きな無力感と絶望感を与えている。
私は、このように歴史や隣国との関係をないがしろにし、人々の間に一世代では乗り越えられないような格差の壁を築き上げている小泉政権の政治を、このまま放って置くことができない。田舎の小さな建具屋の家庭で育ち、真面目にコツコツ働くことの大切さを親父の背中から私は感じてきました。郷土では、自分たちの生活を犠牲にしてまで、子供の夢の実現に協力を惜しまない親たちの姿をたくさん見てきました。生まれた家庭や地域に関係なく、誰もが挑戦できて、その真面目さが報われる社会の実現こそが、格差社会化する日本で、今取り組むべき最も重要な政治課題であると思っています。
自民党の有力政治家のほとんどは2世、3世の世襲議員で、庶民的な生活感覚の欠如ゆえに、人の命の安全や税金・年金についての軽はずみな言動が目立っています。そして難しい政治課題への取り組みの遅れに対する国民の批判をかわすために、近隣諸国への勇ましい言葉でナショナリズムを煽るといった短期的な思慮の浅い政治を行っているのです。国をそうした「現実生活に疎い放蕩息子たち」に任せておくことはできません。民主党が地域の普通の人たちの声を代表し、変化を期待できる新鮮さを打ち出すことによって、政治を普通の人たちの手に戻していく必要があるのです。
私は、多くの日本人がそうであるように、小・中・高と公立学校で教育を受け、田舎出身の様々なハンディキャップを背負いながらも、世界に乗り出して独力で自分を磨いてきました。これまで東南アジアやイギリスで積んできた国際的な経験や知識をもとに、新しい視点もって、閉塞した日本社会に風穴を開けていきたいと思っています。